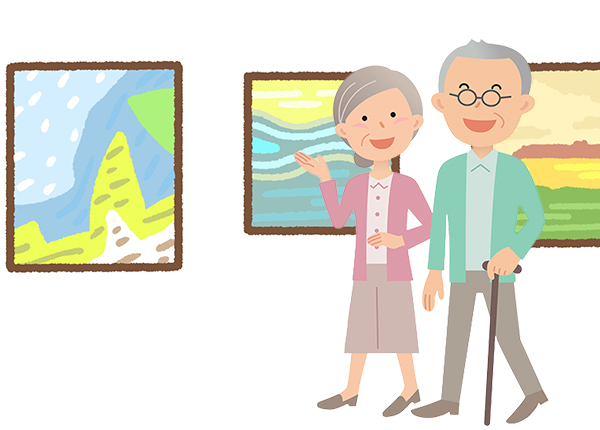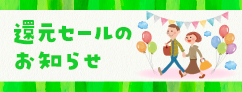- 2026/01/06
第20号 地域で続く「新しい部活」
“引退しない”スポーツ文化につながるか
「〇〇ちゃん、入りたい部活が学校にないから、放課後、電車で別な学校に行くみたい」。長女が中学生だった数年前、そういう話をよく聞いた。うちの場合はたまたま通う学校で部活ができたが、最近では違う学校に行くというシステムを超え、部活動を地域へ移す取り組み「部活動の地域展開(移行)」が全国で進んでいる。背景には、教員の働き方改革のほか、人口減少で1つの学校ではチームが組めないケースなどさまざまな状況がある。そして単なる「外部化」ではなく、これからの日本のスポーツ文化そのものを転換する可能性を秘めた問題でもある。同問題にくわしい田島良輝・大阪経済大学人間科学部教授(スポーツマネジメント)に現状や今後の課題などについて教えていただいた。
―部活動を地域へ移すメリットはどのような点でしょうか。
田島教授 少子化の影響で、1つの学校で1つのチームを結成することが難しくなってきています。地域単位で活動の場ができることで、中学生が「やりたいスポーツ」を継続できる環境づくりにつながります。長野県佐久市の中学校では令和4年、学校で選べる部活が7種目、部活加入率が72%でしたが、部活動の地域展開が進んだ令和7年には12種目、加入率90%に。全体人数は80人から66人に減った中での数字で、少子化の中でも地域のスポーツ環境を維持あるいは向上させ、加入率向上にもつながった1つの例です。
また、これまで学校の部活動では、1つのチームに入ればほかの活動はできなかったり、入りたい部が学校になくてできないという制約もありましたが、地域展開を上手に活用したら、複数種目に参加できる可能性も出てきました。平日は野球部、休日は陸上部ということもできそうです。茨城県神栖市では、市が設置した「地域倶楽部統括管理団体」が、直営する地域クラブ活動と地域の団体や民間事業者のプログラムを認証し、ハイブリッド型の「自主運営型地域倶楽部活動」を提供しています。学校にない種目に触れる機会を週末に持つことができたり、習熟度などに応じてクラブを選択できる側面もあり、中学生の多様なスポーツニーズに対応する新たな仕組みとして期待できると感じました。

―地域展開の現場で、生徒の反応は。
田島教授 休日だけ地域で活動しているところの中学生は「平日は人数が少なくて限られた練習しかないが、土日はたくさんの人がいて、練習内容も充実しているから楽しい」と話していました。また、「参加が義務づけられているわけではない休日に練習しに来る生徒たちからは、『やりたいから来ている』という熱意が感じられる」との感想を持つ指導者もいました。これまでは「やらされる」感がありましたが、地域展開によって生徒の主体性が生まれるのであれば非常に喜ばしいことと思います。
―部活が学校単位でなくなると、試合で勝てなくなるのではと心配をする保護者もいるようです。
田島教授 地域展開の考え方として、「もっとやりたい、うまくなりたい」という生徒を否定しているわけではありません。競技スポーツも生涯スポーツもすべて学校が担ってきたシステムを地域全体で新たなシステムをつくることでサステナブルにしていきましょうという流れであると私は理解しています。そういった意味で、地域の中学生世代のスポーツ環境をどうしていくべきか示すことが重要で、その方向性をまとめていく自治体の役割は大きいと考えています。
―教員の負担についてはいかがでしょう。
田島教授 「教員の時間外在校時間のうち、部活指導の時間が週平均11時間30分短縮」(福井県大野市)「地域スポーツ活動に移行して、業務負担が軽減」(長崎県長与町)「負担が軽減63.6%、どちらかといえば軽減36.4%」(茨城県神栖市)など、一定の効果が出ていることが分かっています。先生の生活にゆとりを取り戻し、授業準備などの本来業務に時間を使えるようになることが期待されます。
―今後の課題は。
田島教授 お金の問題が挙げられます。基本的に無料であった部活動ですが、地域展開になると多くの場合、受益者負担が求められるでしょう。これまでも場所、必要備品、指導者の確保など、スポーツを行うためにはコストがかかっていました。指導者については先生方のボランティア精神に頼り、成立させていたという現実が隠されていました。私自身、スポーツマネジメントを専門としており、価値に見合った対価を支払わなければ、継続できないと感じています。一定の受益者負担については保護者に対してしっかりと説明することが大切だと思います。
地域展開にかかる財源確保については、ほとんどの地域で課題となっており、保護者へのアンケートでは月3000円程度であれば良いという結果も出ています。いくらくらいなら支払うか?という観点も大切な情報ですが、部活動にかかるコストの算出はより重要と考えています。いくらかかるのか分かって初めてそれをまかなうために誰(自治体、受益者、企業など)からどれくらいお金を集めるかという話になってくると思いますので。
―課題を解決するため、どのような取り組みが必要でしょうか。
田島教授 持続性を担保できる仕組みづくりが大切と考えます。学校で行っていた部活をやめる→受け皿になってくれる団体・企業を見つける→その後は団体・企業にお任せ―という流れが地域展開のやり方になってしまうのなら、事実上、単なる部活動の廃止です。「当初受け皿になってくれた団体・企業が撤退したらその後はどうするのか」「想定していた水準の指導者を確保できなかったら」「中学生のニーズから新たに種目を立ち上げる方法はあるか」「そもそもニーズは誰が把握するのか」「けがなどを想定した保険は」など、懸念材料はいろいろ考えられます。それらの問題について情報収集し、調整、解決するコーディネーター、統括するマネジメント組織を置くことが円滑な地域移行の実現の鍵になると思います。地域の状況によって、置くべきであるのが人(コーディネーター)であるのか、組織(統括運営団体)であるのか、あるいは組織が民間企業に委託するのか、もしくは地域のスポーツ事業団やNPOのスポーツクラブに頼むのかなど、形態はそれぞれで良いと思いますが、移行初期の約10年くらいは必要があるのでは。どういう形であれ、コーディネートする人や組織不在ではサステナブルな環境は作れないでしょう。
―神戸市が進める「KOBE KATSU(コベカツ)」では、スポーツや文化・芸術など登録団体が1000団体を超え、保護者を経済的に支援する「コベカツ応援基金」も設立されました。
田島教授 神戸市の取り組みは、大規模な自治体であるにもかかわらず、期限を決めて行動を起こしている点が勉強になります。神戸市として部活動をどのような方向性で考えているのかというビジョンや、そのビジョンを実現するためのマネジメントの仕組みが興味深いです。
―部活動地域展開が進むことにより、地域交流の輪が大きく広がる可能性があります。今後、私たちが地域の担い手の1人として意識すべきことはあるでしょうか。
田島教授 地域交流の輪が広がることは私も期待していて、広げるための契機については今後の自身の研究テーマにもしていきたいです。大人も楽しめる、広い意味で一緒に活動できる場をつくっていけたら良いと思いませんか?1つの学校で1つのチームという従来の形でなく、地域展開は、複数の学校で1チームをつくり、スポーツ環境を維持しようというねらいもあります。串を橫に刺すイメージです。一方で、人口減少のスピードは想像以上に早く、早晩、串を橫に刺してもチームづくりができなくなることが予想されます。そうなったとき、次の手立てとして串を縦に刺す、すなわち多世代で活動していくという策があると思います。
―生涯学習的な仕組みにリンクしていくと。
田島教授 はい。私自身のことですが、小学校でリトルリーグ引退、中3の夏、高3の夏、大学4年でそれぞれ野球部引退と、その都度活動をやめざるを得ませんでした。スポーツを続ける上で悪しき日本のシステムです。地域で続けていける枠組みになれば、中学、高校、社会人と連続的に所属できるクラブができるかもしれません。中学生だけでなく、大人も楽しめる場が生まれ、誰もがいつまでもスポーツや文化活動を存分に楽しめる環境が整うのではと期待がふくらみます。
文部科学省が進める部活動の地域展開はいよいよ2026年度から「改革実行期間」に入る。各自治体の挑戦に注目しつつ、地域単位の活動の中で自分に何ができるか模索してみたいと思う。
コラム「新日常のレシピ」は今号で終了します。
コロナ禍のただ中でスタートした当連載ですが、いつの間にか20回となりました。
5年間ご愛読いただき、誠にありがとうございました。
皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
青木理子