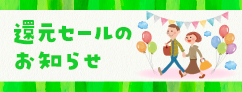- 2023/07/03
- 未分類
第10号 ズボラでも挑戦!リサイクル
スーパーなどの店頭で、リサイクルボックスをよく見掛ける。ペットボトル、食品トレー、牛乳パック。内容ごとの箱がずらりと並び、投入口いっぱいまで容器が詰まっていることもある。
ある店のホームページをチェックしてみたところ、回収後、ペットボトルは卵パックに、トレーは固形燃料に、牛乳パックはトイレットペーパーに再生されていると分かった。さらに食用油は、精製されて液体せっけんになり、店舗で使われていた。時々使わせてもらっているあのせっけんが、元は天ぷらを揚げた後の油かもしれないとは。具体的に何に生まれ変わっているかを知ると、ワクワクする。
と言いつつ、恥ずかしながら私は店頭リサイクルボックスを利用したことがほとんどない。理由は…正直に言うと、容器類をきれいに洗って、乾かして、袋などに入れて、スーパーに買い物に行く際に忘れずに持参する、というところまで気力が湧かない。いやもっと細かく言うと、洗うのはなんとかできるかもしれない。袋に入れて、店に持参も習慣化したらできるだろう。ネックは、洗ったものを乾かすスペースがないことだ。皿1枚増やすのも躊躇するわが家の手狭なキッチンの中で、たくさんの空容器を乾かすスペースを捻出することは非常に難しく思える。
近年、リサイクルの取り組みは飛躍的に進んでいる。特筆すべきは、使用済み製品を同じものに再生する「水平リサイクル」だ。一般的なリサイクルが別な製品への再生をくり返した後、最終的にごみとして処理されるのに対し、水平リサイクルは、元の製品に使える品質の素材に戻して再び原料とするため、新たな資源の消費を抑えられるメリットがある。
「水平―」の中でも注目を集めているのが、神戸市の「神戸プラスチックネクスト」である。同プロジェクトは、洗剤やシャンプーなど使用済みの日用品の詰め替えパックを分別回収、再び詰め替えパックに戻す「つめかえパックリサイクル」、プラ資源の回収と地域の人々の交流を兼ねたスポット「資源回収ステーション」の設置、家庭から回収した使用済みペットボトルを新たなペットボトルに戻す「ボトルtoボトル」の3本柱で推進。プラスチックの水平リサイクルを目指し、同市と各社が協力しながら取り組んでいる。
そのほか全国を見渡すと、「使い終えたタイヤを合成ゴムなどの原料に戻す」(ブリヂストン)、「使用済みクリアホルダーを再製品化」(アスクル)なども。循環型社会に向けたチャレンジがあちこちで行われている。
とはいえ、リサイクルは、企業側の努力だけでは成り立たない。資源となるごみを出す人の意識が重要だ。
「プラスチックごみについて」と題した神戸市ネットモニターアンケート(2020年、3,136人回答)によると、プラスチックごみ問題に「関心がある」と答えた人は約34%、「ある程度関心がある」は約50%で、8割以上が同問題に関心を寄せていることが分かる。
だが、店頭回収を利用している人は約51%。利用していない人約49%をわずかに上回った数字に止まっている。ごみ問題に関心がある人は多いものの、実際に店頭回収に協力するには、ハードルを感じる人も少なくないようだ。
話を私自身に戻す。積極的に「リサイクルに出したい」と思うものが2つある。それは、卵パックとミニトマトが入ったプラスチック容器だ。どちらも基本的に汚れておらず、洗う必要がほとんどないため、干す場所も要らない。一方で、プラごみの袋に入れると、ほかのプラがあまり入らなくなるほどかさばる。そのため、「この2つは、リサイクルボックスに」といつも思う(発想がズボラで、重ねてお恥ずかしいのだが)。

SDGsに関心がないわけではないが、日常的にリサイクルに協力するところまではいけない、私のような層。そういう人たちが一歩前に踏み出せるきっかけはないか。
「神戸プラスチック―」で詰め替えパック回収に携わっている、小売り各社の担当の方に「干し場問題」についてご相談してみた。
とくにシャンプーなどの詰め替えパックは、洗うのに手間が掛かる。そこで、「パックを半分に切って洗い、物干し竿で洗濯物といっしょに乾かしています」(「光洋」総務部の林麗子さん)。「パックの袋にハサミを入れてアジの干物みたいに全部開いて、1枚の板状に。それをお風呂場で洗って干す。水を切りやすいです」(「ウエルシア薬局」総務部の朝比奈恵美さん)。実践的なアドバイス、ありがとうございます!
お2人によると、リサイクルに関わるアイデアは、お客さんや店舗スタッフに教えてもらうことが多々あるという。すべての人が立場を超え、知恵を出し合い、協力して初めて、リサイクルは実現する。その過程を楽しみながら、できることから取り組んでいきたいと思う。
(文・青木理子)


 ペットとして輸入されたものが遺棄され、日本各地で見つかっているカミツキガメ。今のところ関東の河川や湖沼などで定着が確認されている。今後、関西でも定着が確認されるかもしれない。
ペットとして輸入されたものが遺棄され、日本各地で見つかっているカミツキガメ。今のところ関東の河川や湖沼などで定着が確認されている。今後、関西でも定着が確認されるかもしれない。